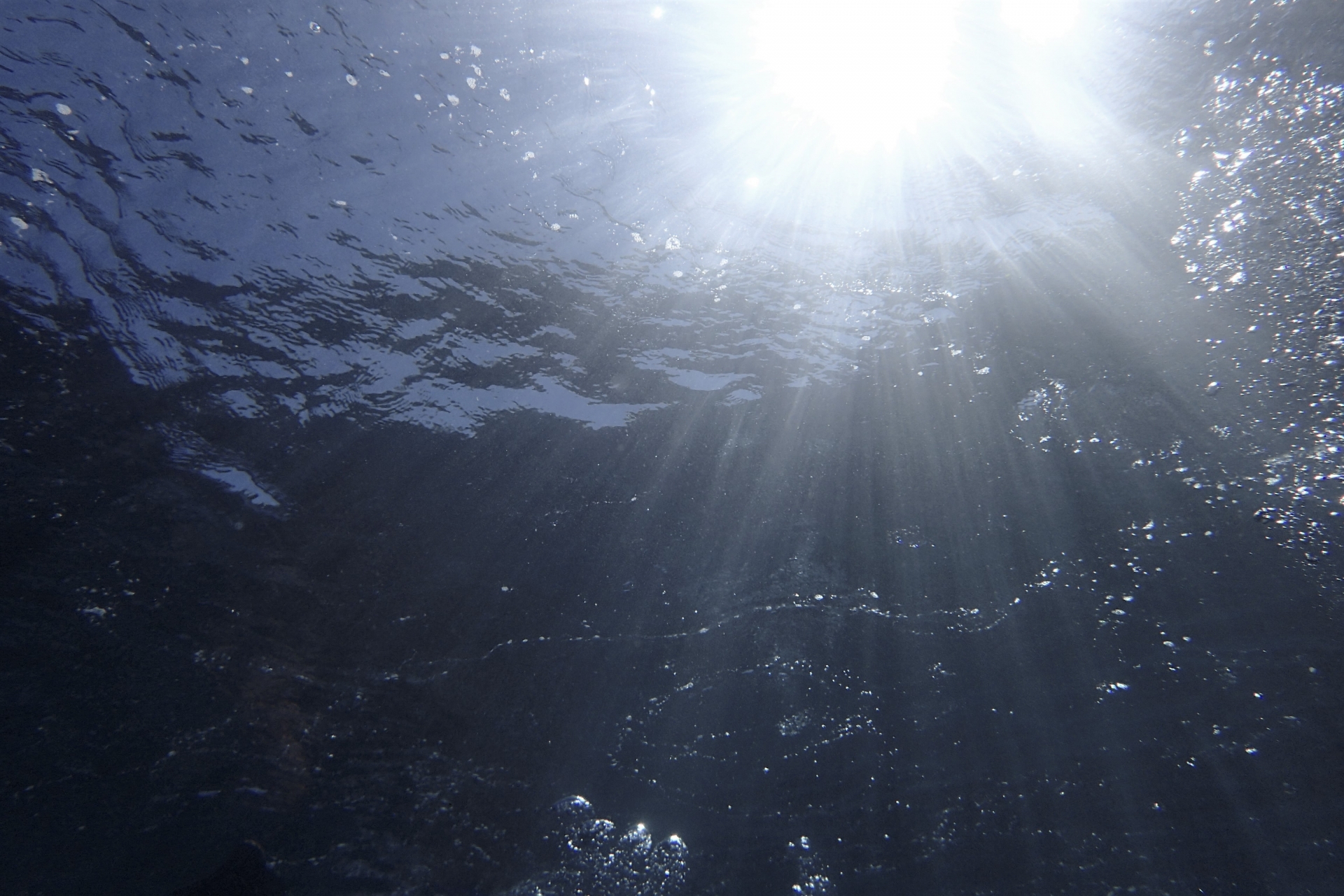クラフト袋のコストダウンを図る。
例えば、紛体やペレット(小さな固形物)などのような原材料を入れるためによく使われる大きな紙袋があります。米袋やセメント袋をイメージしてもらうとよくわかると思うのですけど、その袋をクラフト袋と呼んでいます。


クラフト袋を使用されている生産現場では、袋のサイズや中身が同じであったとしても仕向け先やサイズに応じて印刷を変えて袋を制作し、その銘柄ごとに受け容れ、管理されているのが一般的です。 また、作業現場では、概ね、こんな流れで扱われている場合がほとんどだと思います。
こういった作業が担当者の日常業務として一般的に行われています。
で…. この一連の作業の中のどこにコストダウンのポイントがあるのか? と言うと、ズバリ! 作業そのものなのです。 では、なぜ、作業そのものがコストダウンのポイントになるのか? それを詳しくお伝えしますね。