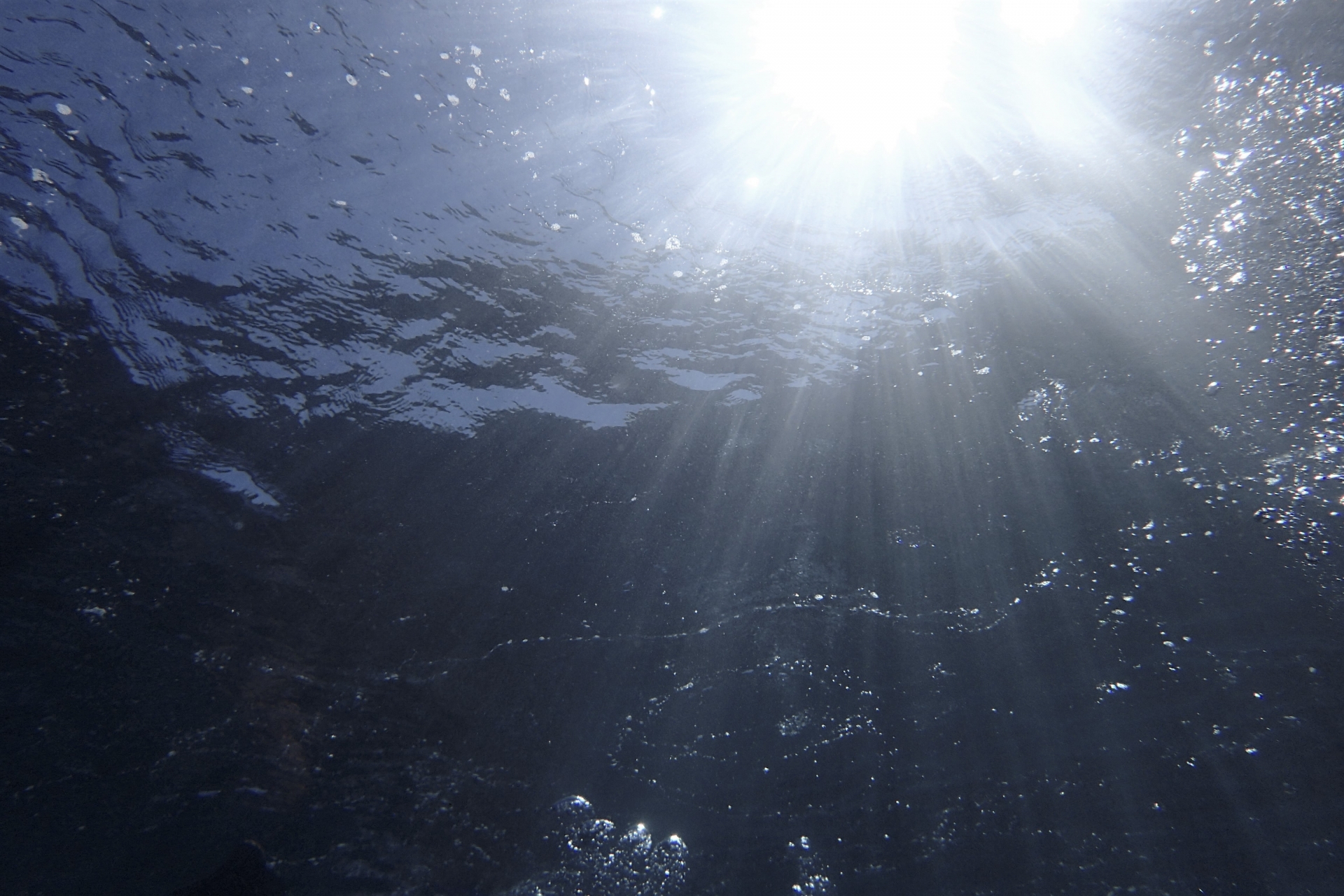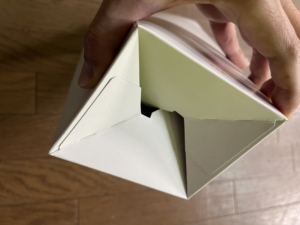こんちは、
マーキングコトはじめ、担当のけたろーです!
今日もありがとう、感謝です。
さて、本日の話題は、
段ボールなどの副資材のコストダウン(・・の可能性)についてです。
段ボールなどの副資材のコストダウン(・・の可能性)についてです。
甥っ子がアパートから荷物を引き上げて、うちの工場に置いていったのですが、
その荷物を見ていてちょっと思ったことがあるんです。
引っ越し用にスーパーからもらってきた某菓子メーカの段ボールが、
ふと、目とまって、
おや、おや? コストダウンできるのに・・もったいなぁ!
と、思ってしまったんですよ。これって、職業柄なんでしょうねぇ。
あ、段ボールって、こんな感じです。