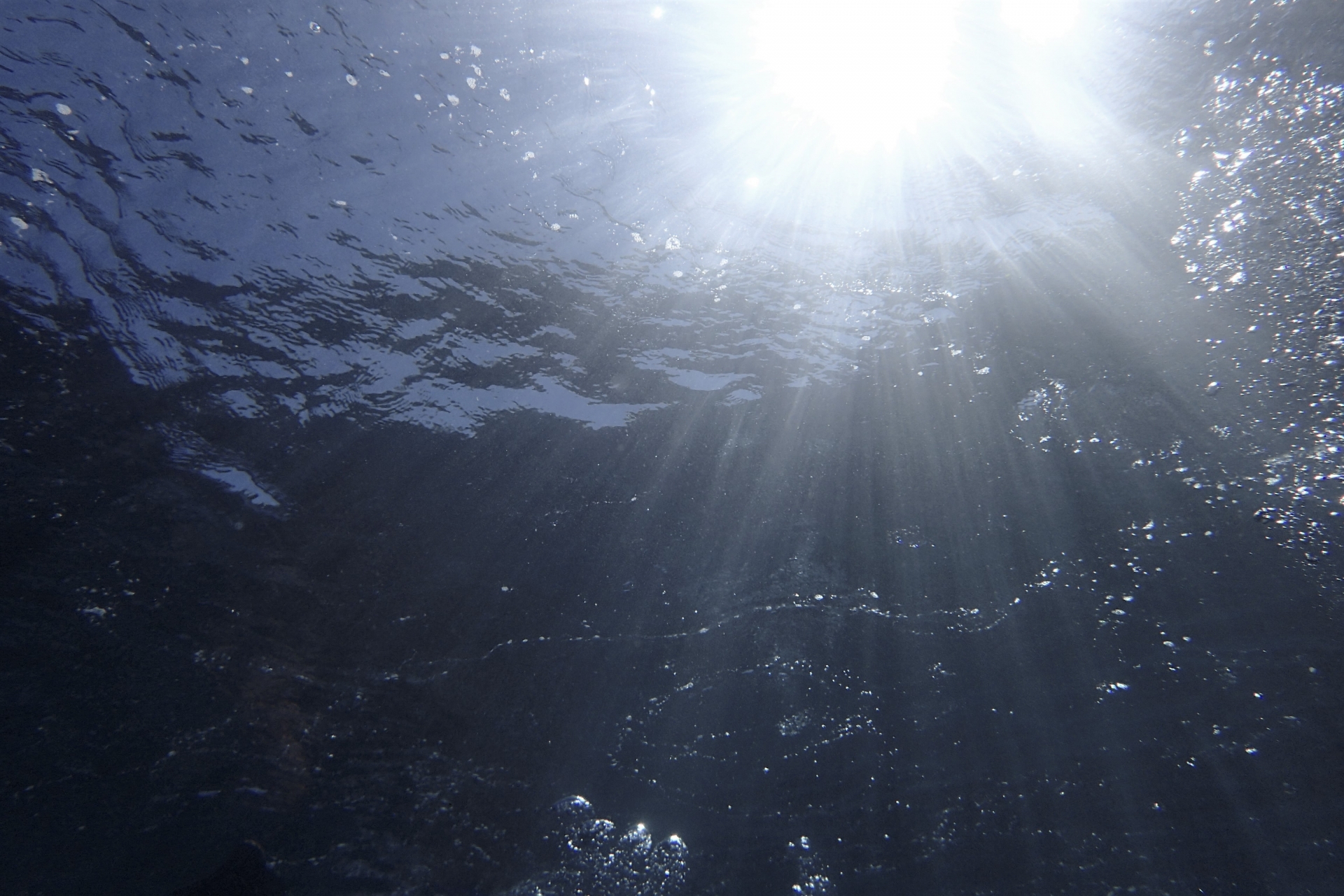最幸最善の改善策!

包装副資材のコストダウンを図るとっておきの方法・・・ それは、
です。
産業用インクジェット(以下IJP)や、レーザーマーカー(以下LM)は、ただ、ロット番号や賞味期限などといった文字を描くためだけの装置ではありません。 使い方によっては包装資材のコストダウンに大きく貢献してくれます。
IJPやLMの特性は、オンデマンドでのダイレクト印字(※)ができること。その特性をうまく活用すれば、包装資材への大きなコストダウン化が図れるのです。(※ その都度、印字内容を書き換え、対象物に直接印字を行うこと。)
もっとも… ここまで述べてきた〝包装副資材〟というのは、内装用のカートン小箱や外装用途の段ボール資材のことです。
これらの包装副資材は、一般消費者の目に留まるわけでもなく、あくまで流通用途が主な目的ですよね? 意匠などに特に問題がなければ、今からお伝えする方法が恐らく最幸最善の方法になりえます。
小箱や段ボールなどの輸送用途で使用する包装資材のコストがかかってしまう大きな要因のひとつが、品種銘柄ごとに箱を制作してしまうことにあります。 たとえ、内容物のサイズが同じでも、銘柄が2種以上あればその種類分の資材を制作してしまうことが問題なのです。
もしくは、現状1品種での運用が、品種が増えてきた際にそれを整理することなく、都度、資材の種類を増やして対応してしまうということにも問題があります。
ではまず、【コスト】についての概念を整理しておきましょう。 包装資材に係るコストとは? 下記が挙げられます。
- 包装資材の紙質、質感、形状など、資材そのものに係るコスト。
- 包装資材を保管・管理していくための設置場所へのコスト。
- 包装資材をハンドリング(出し入れ)するための労力(人件費)。
ザクッと、こんな感じですよね。
包装資材そのものコストは仕入れのコストになりますので一番わかりやすく、目に留まりやすいコストだと思います。
しかし、重要なのは、それ以外の2項目です。 保管・管理に係る費用やハンドリングのための労力は、目につきにくいコストでもあり、一番大きなウェイトを占めています。 要は、その部分を改めることができれば、包装副資材に係るトータルコストが削減できるというわけです。 これを進めていく上でのポイントは、
包装副資材のサイズと印字する内容を整理すること。
共通化できるところを共通化して、それ以外のところをIJPやLMを使って対応するというわけです。
例えば、会社ロゴなどは各品種によって共通でしょうから、それは〝プレ印刷(※)〟として対応し、品種銘柄はタイトルが変るので、都度印字するといった方法です。 ※予め印刷する内容。
こうすることで、同一サイズであっても銘柄ごとに発生していた仕入れや、銘柄に分けていた管理がなくなります。 つまり、その分のコストが下がるということです。 また、プレ印刷部分を共通化することで印刷個所の削減につながり、それに伴い、包装資材の制作コストが下がります。 すなわち、資材単価が下がるのです。
また、同一サイズであっても品種毎に分けていたオーダー枚数を1品種で集中的にオーダーできるため、バリューメリットも期待できます。
どうでしょうか? 過去の事例をまとめていますので、よければ下記の記事も参考にしてください。