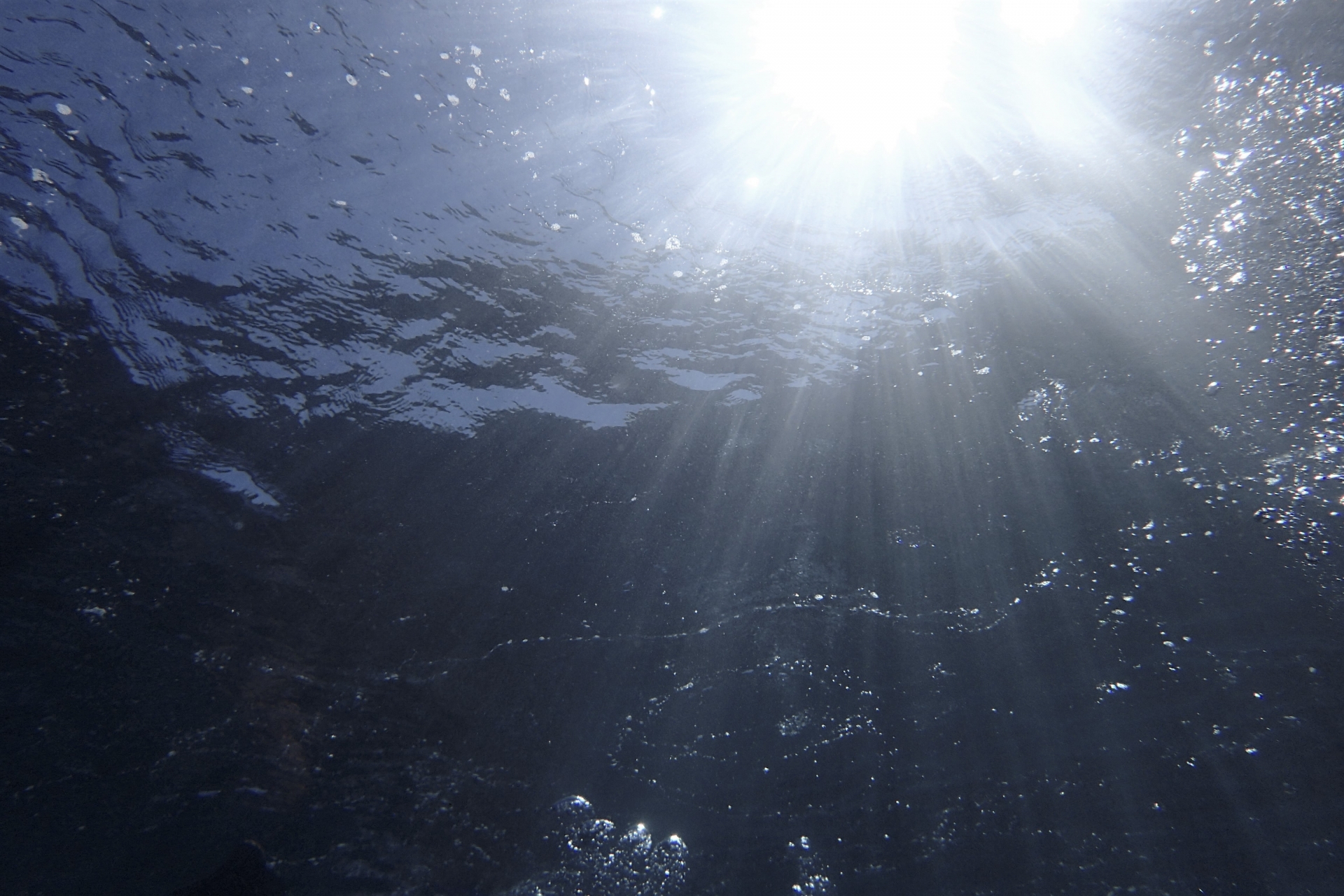カートンや段ボールケースのコストでお困りのあなたへ。

商品の種類が増えるたびにケースのデザインを考え、対応してきた結果、気が付けばケースの種類が膨大になってしまってて。廃盤になってるものとか、デッドストックもたくさんあるみたい…。
なんとかならないでしょうか??
そんなお困りごとでちょくちょく相談に来られる方が増えてきました。
商品点数(アイテム)が少ない時にはプレ(事前)印刷で対応していても、それほどの管理ボリュームではなかったのでしょうけど、アイテムが増えてくるとアイテムごとの仕分け管理が必要になってきて保管するスペースも大きくなってきますよね。
種類やボリュームが増えてくると必要なモノを探し出す作業など、結構、手間暇=労力がかかってきます。
実は、この状況の中に2つの問題が隠されています。 なんだか、わかりますか?